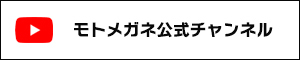バイクのマフラーカスタムは、見た目をかっこよくしたり音を楽しんだりするために人気ですが、実は守らなければならない基準があり、その複雑さに悩んでいる人も多いでしょう。特に排ガス規制や音量規制は重要で、年式によっても基準が異なることがあります。これを知らずにカスタムすると、後でトラブルになることも。
本記事ではバイクのマフラーカスタムについて、年式ごとに違う規制の内容などをくわしく解説していきます。
年式ごとの騒音規制値
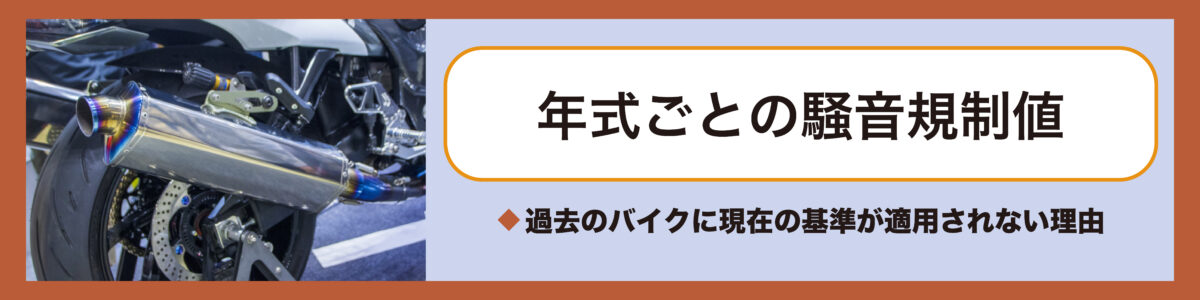
バイクのマフラーについては製造年式によって騒音規制値(dB表示)が変化します。まず騒音規制値にある「dB」とは音の大きさを表す単位です。たとえば騒音規制値99dBは、電車が通る時のガード下(100dB)と同じくらいの音の大きさです。
また年式ごとのマフラーの騒音規制値については、製造年が新しくなるほど騒音規制値は小さくなっており、騒音に対しては年々厳しくなっているのが現状です。
250cc以上のバイクのマフラー騒音規制値を例にすると、騒音規制基準は次の表のように推移しています。
| 近接排気騒音法基準値(移行期日) | ||||
| バイク種別 | H10(1998)年規制以前 | H10(1998)年規制 | H13(2001)年規制 | H22(2010)年規制 |
|---|---|---|---|---|
| 排気量250cc以上 | 近接99dB | 近接99dB | 近接94dB | 近接94dB加速82dB |
引用:JMCA公式サイト「騒音規制値について」(2024年10月3日現在)
表からもわかる通り、年式の古いバイクは騒音基準が緩く設定されています。バイクの排気音がバイクを選ぶポイントの1つであれば、年式も考慮してバイク選びをするのもオススメです。
過去のバイクに現在の基準が適用されない理由
上段ではバイクが出すマフラー騒音の点からみて、規制を説明しましたが、過去のバイクに対して現在の基準が適用されない理由は、既得権の存在です。
当時の法的根拠に基づいて流通を許されたバイクを、後出しの法律により乗れないようにしてしまうと、国が国民の権利を奪う形になってしまいます。そのため、過去のバイクには過去の規制が適用され、最新の基準は最新のバイクにのみ適用されます。
排ガス規制に適合しているかの確認にはガスレポが必要
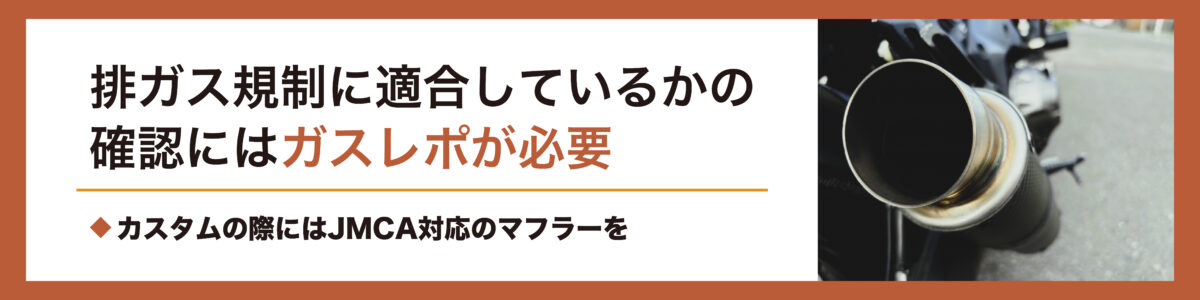
ガスレポとは、「自動車排出ガス試験結果証明書」のことを言います。自動車排出ガス試験結果証明書はバイクを含めた車両が排出するガスの濃度(CO、HC、NOxなど)を測定した試験結果を示したものです。
バイクのマフラーを純正品から社外品に交換した場合、WMTCモード(二輪車の燃費を計算する際に用いられる国際的な走行モード)適用車がキャタライザー(触媒:エンジンから排出される排気ガス中の有害成分を無害化して浄化する役割を担うパーツ)を変更した場合にガスレポ提出が必要です。
しかし純正キャタラライザーを使用している場合はガスレポの提出義務はありません。
カスタムの際にはJMCA対応のマフラーを
まずJMCAとは、正式にはJapan Motorcycle Accessories Association(一般社団法人全国二輪車用品連合会)の略称のことを言います。
JMCAは国内大手二輪車用品メーカー・卸・小売などの会員で構成され、バイクの排気騒音問題について、環境省や経済産業省、国土交通省、警察庁などからの協力のもとで不法製品の一掃などを目的として活動している団体です。
なので、マフラーカスタムでなにか心配ごとがあれば、JMCA対応のマフラーを選んで装着すれば騒音問題を含めすべてにおいて問題はないでしょう。JMCAの公式サイトに「マフラーに関するQ&A」がありますので参考にするとよいでしょう。
引用:JMCA公式サイト(2024年10月3日現在)
まとめ
本記事では、バイクのマフラーを交換するのに注意したい騒音などの規制値についてマフラーの製造年式別に解説しました。純正マフラーを社外品マフラーへ交換すると、見た目はもちろんのことパワー・トルク・マフラー音などでルックス以外のライディングに直接機能することから、改造のポイントが大きいことは事実です。
しかし、マフラーの交換については海外マフラーや公道走行不可のレース用マフラーなどを装着すると騒音規制に適合しなくなり、警察から指摘される可能性もあります。マフラーをカスタムする際は、バイクの使用目的に合わせてJMCA公認・車検対応のモノを選べば間違いはないでしょう。