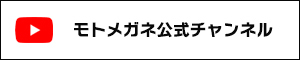信号機といえば、多くの人が青黄赤と横に並んだものをイメージするかもしれません。しかし、じつは雪国では縦型の信号機が一般的です。
今回は、雪国に縦型信号機が存在する理由や、そこにみられるさまざまな工夫を紹介します。
縦長信号機が存在する?いったいなぜなのか

ウインターレジャーなどで雪国を訪れると、信号機が「横」ではなく「縦」になっていることに気づく人も少なくないでしょう。普段横型の信号機しか目にしない人にとっては珍しい景色に思えますが、これは雪国に住む人々にとっては当たり前の光景です。
では、そもそもなぜ雪国では縦型信号機が使用されているのでしょうか。理由として、信号機に雪が積もらず見やすいことが挙げられます。
雪が積もってレンズを隠してしまわないようにするため
一般的な横型の信号機は、レンズの上部に太陽光をさえぎるための庇(ひさし)がついています。しかし横型信号機は、庇の上に分厚い雪が積もると雪が垂れ下がり、3色全てのレンズを隠してしまうことになってしまいます。
そこで、庇が垂直に並ぶ縦型信号機だと雪が積もる面積が少なくなり、レンズが隠れることがないというわけです。
また、横型信号機だと雪の重みで支柱が折れたり、信号機そのものに悪影響を及ぼしたりする可能性もあります。こういった保守の面からも、雪の積もる量が少ない縦型のほうに軍配が上がります。
ただ、縦型信号機にも、問題がなかったわけではありません。
実は縦型信号機にも問題があった!
たとえば、豪雪に対応するために庇を長くして対処する信号機も存在するようです。また、庇に積もった雪がその上のレンズを隠してしまうこともしばしば。
そこで、いちばん上にある赤のレンズはそのままに、それ以外の庇を短くして雪の積もる量を減らすことで、真上のレンズを見やすくした地域もあるといいます。
このように、これまでも雪国の信号機は雪に対してさまざまに工夫がこらされてきました。そしてLEDの登場により、信号機は薄く、軽く、小さく進化しているようです。

近年のLED信号機は薄型フラット信号機と呼ばれており、厚みが10センチもなく上部に雪が積もりにくい設計です。また、LEDは太陽光の逆光に強いので庇もありません。
ところが、LED灯といっても万能ではありません。従来の白熱電球は45度の熱を発しますが、LEDは20度しか放熱しないためレンズ表面についた雪が解けにくいのです。
さらに豪雪地帯では別の対策が
つまり、大雪に見舞われると信号機のレンズ面が雪で覆われ、どの色も「白」になってしまうことも少なくありません。しかしこのまま放置しておくと事故の原因にもなるため、北海道では警官が長い棒を使い、表面の雪を取り払っています。
さらに山形県では、赤レンズの部分にだけ雪を溶かす電熱線を貼ったLED信号機を採用しているようです。
なお、ほかにもレンズに透明なカプセルを取り付けたLED信号機も登場。カプセルによって、雪がついても落としやすく設計されています。
また、信号機の薄さと軽さを活かして、信号機自体を前傾させて取り付けるタイプも存在します。こちらのタイプは垂直な信号機よりも雪が下に落ちやすくなる点が好評を博しているようです。
ちなみにこうした信号事情は、地域の雪質によっても異なります。たとえば日本海側で降る雪は北海道のようなさらさらで乾いた雪とは異なり、湿気が多くレンズ面につきやすい傾向にあります。
事故を減らすためにも、信号を見やすくしたいという試行錯誤が続くなか、雪国ではそれぞれユニークな縦型信号機がみられそうです。